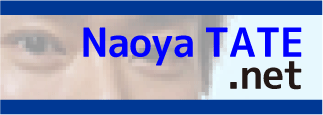Q&A:
| Q1 コアタイムはありますか? |
| A1 原則として、各学生の自主性に任せています。 日常的な連絡はSlackやTeams等を通じて行いますので研究室に来ずともあまり支障はありませんが、 一般的には、研究室によく来る学生の方がよりコンスタントに研究を推進できていると感じます。 研究というものは決して一人でできるものではないので、研究室という環境で他の学生とコミュニケーションをとれた方がよりはかどるのは間違いないです。 |
| Q1 ミーティングはどれくらいの頻度でありますか? |
| A1 週1回程度研究室メンバー全員が集まって、「雑誌会」と称する勉強会・発表会の機会を設けています。 それとは別に、各自の研究内容や実験内容について議論するためのミーティングを、テーマごとに2週に1回程度のペースで実施しています。 |
| Q2 卒業生はどのようなところへ就職してますか? |
| A2 各学生の研究テーマの内容に依らず、多種多様な業界・業種に進んでいます。 具体的な進路の一部は「これまでの在籍メンバー」ページに記載していますので、必要に応じて参考にしてください。 |
| Q3 光について、どれくらいの基礎知識があればやっていけますか? |
| A3 学部講義で当研究室のテーマと関係性が深い科目は「光学・フォトニクス基礎」および「光エレクトロニクスI」、「同II」ですが、仮にこれらの科目を未履修だったとしても 研究室配属後に新入生を対象に実施する「光学系研究室合同学生ゼミ(勉強会)」を通して光に関する基本的な知識を習熟できますので全く問題ないです。 |
| Q4 半導体に興味があるのですが、この研究室と半導体は関係ありますか? |
| A4 分野としての「半導体」というワードは非常に含意が大きく、現代において「半導体」と全く無関係の研究はあまりないと思います。 例えば「半導体材料」という枠組みであれば、当研究室でキーテクノロジーの一つとして取り扱っている「量子ドット」は 蛍光性の「半導体」微粒子として昨今多様に活用されている材料です。 さらには、SiC(シリコンカーバイド)という、高耐熱・高耐圧・高放熱に非常に優れた「半導体」基板を用いた新しい光デバイスの開発も行っています。 また「半導体業界」という枠組みにおいては、当研究室では「半導体」チップの製造から流通に至る一連の流れ(サプライチェーン)における安全・安心を確立するための 高度な光認証技術の開発を進めています。 |
| Q5 プログラミングが好きなのですが、この研究室とプログラミングは関係ありますか? |
| A5 どの研究テーマにおいても、データ解析、シミュレーション、システム設計・制御、機械学習等々、相応にプログラミングを活用する機会があります。 特に当研究室では、新しい光システムを構築するにあたり、その設計と評価に際してプログラミングに特化したテーマを設けるケースもありますので、 プログラミングが得意な学生にはそのようなテーマで持ち味を発揮してもらうこともあります。 |
| Q6 博士課程進学に少し関心があるのですが...。 |
| A6 博士号とは、自身が研究のプロフェッショナルであることを証明するものです。 逆に言えば、博士号を取得していなければプロとしては認めてもらえません。 電気情報工学科からシステム情報科学研究院へ進学して社会に出ていく上で、全く分野外の仕事に従事するつもりなのであればその限りではありませんが、いわゆる「理系的な職種」につくことをなんとなく想定しているのであれば、本研究室では博士課程進学を強く推奨します。 昨今社会や産業の変革が目に見えて著しい中、皆さんが社会に出て活躍しなければいけない頃には、その流れが一層加速しこそすれ、収束するような時勢には絶対になっていないだろうと想定されます。 修士卒で就職する学生の比率が高いのは事実ですが、そのような時勢に際して皆と横並びで「アマチュア」のまま臨むというのが果たして正しい選択なのかどうかについては、現時点で博士課程進学を全く想定していない学生も、改めて考えてみてください。 |
| ※上記の他に当研究室の活動等に質問があれば、メール(tate[at]ed.kyushu-u.ac.jp)もしくは問い合わせフォームより気軽に連絡してください。 |